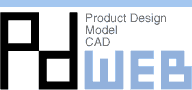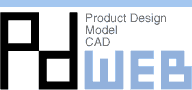芝 幹雄
1983年多摩美術大学デザイン科卒業、GKインダストリアルデザイン研究所に入社。1990年株式会社GEO設立に参加、医療機器の設計とデザイン、その他産業機械の設計を手がける。2007年3月独立、株式会社SHIFT設立。同社代表取締役。
http://www.shift-design.jp/ |
 |
●高品質なドイツのデザイン
「Form・Follows・Emotion」、つまり形態は情緒に従うということになる。そう言ったのはブラウンのデザインディレクターであるピーター・シュナイダーである。
我々の世代のデザイナーにとってブラウンの製品はデザインの教科書のようなものであった。まさにモダニズムの具現化であり、またその優れた生産技術にも目を見張るものがあった。特に記憶に残っているのは電卓だ。シンプルで機能的なデザインを真似をすることは出来ても、その成型技術に関しては当時の日本ではとても真似のしようがなかった。
1980年代の日本はもう工業大国と世界から認められ、アメリカとの間で貿易摩擦が問題化していた頃である。それは安価で価格以上の価値があるものを大量に作り出す術は十分に持っていた証拠でもある。
しかし、高品質と言う点ではドイツに及んでいなかったようである。その後十数年でようやく、品質に於いてもドイツと肩を並べることが出来るようになったわけであるが、超えたと言う実感は現在でも、いろいろな製品を比較してもなかなか確実なものとはならない気がする。
●形態は情緒に従う?
当時のデザインディレクターはミスターブラウンと呼ばれたディーター・ラムスである。デザイナーで彼の名を知らない人はいないであろう。彼のデザイン哲学は「Less・but・better」であった。そして、当時のブラウンの製品は世界中のデザイナーから注目されるデザインの手本となった。しかし昔のブラウンのデザインを知る人たちは、その質の高さは変わらないものの、ここ10年ほど間のブラウンのデザインの変化にお気づきのことであろう。
ディーター・ラムスはデザインディレクターの座をピーター・シュナイダーに譲り1997年にブラウンを退社している。
そしてピーター・シュナイダーはブラウンのデザイン思想の看板を「Less・but・better」から「Form・Follows・Emotion」に取り替えた。彼自身がそうしたいと望んだことかどうかは分からないが、それまでの流れを変える必要に迫られていたのではないだろうか。彼が見たものはモダニズムの限界と言えるのかもしれない。つまりモダニズムの規範の中では世界のマーケティングに合致する製品を作り出すことが出来なくなり、そこから一歩踏み出さざるを得なかったのかもしれない。
ブラウンは随分前にアメリカのジレットグループの傘下となっている。そんな背景が彼にあのように言わせたとすれば、理解出来なくもない。
彼は「Form・Follows・Emotion」と言う言葉によって何を語りたかったのであろうか。「形態は情緒に従う」という直訳的な言葉の意味だけをとらえるならば、どうしても疑問が残ってしまう。人間の情緒ほど、あてにならないものはない。自分自身の感情分析すら難しいのに。他人の感情を論理的に分析出来る人がどれだけいるだろうか。
●Emotionと言うキーワード
人間の脳は右脳と左脳に分かれ、それぞれ感情的思考の分野と論理的思考の分野に役割を分け、脳梁と呼ばれる神経回路によってつながれている。ここで随分と情報の絞込みが行われているらしい。進化の過程でそのようになったのはそれなりに理由があるのだろう。脳梁が左右の情報を多く伝達しすぎると、人間は精神分裂になってしまうらしい。
そのようなわけで、もともと感情と論理は相容れないことが多い。理性的には理解出来ても、感情的にはどうしても受け入れられないなどと言うことは良くあることで、またその逆もある。しかし両者が一致する時もある。それは今まで意識せずに深層心理の中で何かを求めていて、ある光景やモノを目の当たりにした時それに気づいたときなどが良い例ではないだろうか。そんなとき人は感動したり、妙に納得がいく気分になったり、それに続く別の衝動が沸き起こったりする。
マーケティング的に言えば潜在需要の中の購買力が伴わず有効需要とならないもの以外にあたり、まだ目にしたこともないため、あるいは考えたこともなかったため、欲しいと思わないもの。そのようなモノの存在を示している。通り一遍のリサーチでは決して顕在化しない部分であり、マーケティングとデザインの永遠のテーマであろう。
それをいとも簡単に解決してしまいそうに思わせる言葉がEmotionと言うキーワードであり、ある時期世界中で流行った。だが当然のこと誰もそこから方程式など導き出せていない。その言葉によってデザインはより自由になったのは確かであるが、商品開発に博打的な要素を持ち込んでしまったのも事実である。
いずれにしてもデザインの世界では最も取り扱いに注意を要するキーワードと言えるのではないだろうか。
 |