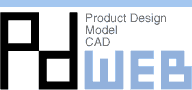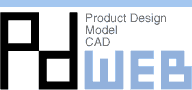pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン
●今、気になるプロダクト
その30:モジュールを組み合わせてモノを作る「LittleBits Synth Kit」
その29:水縞「全国架空書店ブックカバー」をめぐって
その28:ESPのGrassroots ピックガードギター「GR-PGG」が面白い
その27:米ナッシュビルのハンメイドギターピック「V-PICKS」
その26:キリンビバレッジ「世界のkitchenから」をめぐって
その25:「UP by JAWBONE」をめぐって
その24:「未来の普通」を実現したツール、Livescribe「wifiスマートペン」
その23:スマホでは撮れない「写真」を撮るためのコンデジ「EX-FC300S」
その22:真剣に作られた子供用ギターは、ちゃんとした楽器になっている「The Loog Guitar」
その21:紙をハードウェアとして活かしたデジタル時代の紙製品
その20:Kindle paperwhite、Nexus 7、iPad miniを読書環境として試用する
その19:未来の形を提示したヘッドフォン、Parrot「Zik」を考察する
その18:iPadなどタブレット用のスタイラスペン3タイプ
その17:カプセル式のコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」
その16:iPadで使うユニークなキーボード、3種
その15:紙のノートと併用できるオーソドキシーのiPad用革ケース
その14:今世界一売れているボードゲーム「エクリプス」に見るインターフェイスデザイン
その13:SimplismのiPhoneカバー「次元」シリーズ
その12:3,000点の展示数は当然だと感じられる「大友克洋GENGA展」
その11:大人が使って違和感のない文具、「Pencoのディズニーシリーズ」の魅力の秘密に迫る
その10:VOXのトラベルギター「APACHE」シリーズをめぐって
その9:業務用スキャナのScanSnapモードを試す
その8:シリーズ「iPhoneに付けるモノ」:iPhoneの録音周りを強化する
その7:フルキーボード搭載の新ポメラ、キングジム「DM100」
その6:取材用ノートケース製作録
その5:40年間変わらないカップヌードルというモノ
その4:インターネット利用のモノ作り「Quirky」の製品群
その3:最近の保温保冷水筒をチェック
その2:「スーパークラシック」と「スーパーコンシューマー」の文具たち
その1:五十音「Brave Brown Bag」
Media View
●秋田道夫のブックレビュー
第22回:「だれが決めたの? 社会の不思議」
第21回:「思考の整理学」
第20回:「デザインの輪郭」
第19回:「デザインのたくらみ」
第18回:「覇者の驕り―自動車・男たちの産業史(上・下)」
第17回:「素晴らしき日本野球」
第16回:「建築家 林昌二毒本」
第15回:「ブランディング22の法則」
第14回:「中国古典の知恵に学ぶ 菜根譚」
第13回:「プロダクトデザインの思想 Vol.1」
第12回:「先生はえらい」
番外編:「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
第11回:「知をみがく言葉 レオナルド・ダ・ヴィンチ」
第10回:「ハーマン・ミラー物語」
第9回:「ポール・ランド、デザインの授業」
第8回:「プロフェッショナルの原点」
第7回:「亀倉雄策 YUSAKU KAMEKURA 1915-1997」
第6回:「I・M・ペイ―次世代におくるメッセージ」
第5回:「ル・コルビュジエの勇気ある住宅」
第4回:「芸術としてのデザイン」
第3回:「天童木工」
第2回:「アキッレ・カスティリオーニ 自由の探求としてのデザイン」
第1回:「柳宗理 エッセイ」
Tool View
●魅惑のレンダリングワールド
第6回:Maxwell Renderを用いた小坂流ビジュアル術
第5回:Maxwell Renderの概要
第4回:nStyler2.1をより使い込む
第3回:さらにパワーアップしたnStyler2.1
第2回:Hayabusaのレンダリング画像
第1回:Hayabusaの概要
●[集中連載]SolidWorks 2008レビュー!全4回
最終回:「フォトリアルなレンダリング画像を作る」
第3回:「レイアウト」検討からの部品作成
第2回:サーフェス上スプラインとソリッドスイープ
第1回:インターフェイスやモデリングの概要
LifeStyle Design View
●さまざまな日用品
第1回:空想生活「ウインドーラジエーター」
●IHクッキングヒーター
第3回:「MA Design」
第2回:「空想生活COMPACT IH」
第1回:「東芝MR-B20」
●オーディオ
第3回:「TEAC LP-R400」
第2回:「amadana AD-203」
第1回:「JBL spot & Jspyro」
●ライト
第5回:「BIOLITE EON」
第4回:「TIZIO 35」
第3回:「ITIS」
第2回:「Highwire 1100」
第1回:「Leaf light」
●トースター
第4回:「ZUTTO」
第3回:「VICEVERSA」
第2回:「±0」
第1回:「Russell Hobbs」
●コーヒーメーカー
第6回:「±0」
第5回:「MA Design」
第4回:「ZUTTO」
第3回:「deviceSTYLE」
第2回:「Rowenta」
第1回:「Wilfa」
●ハードウェア
第3回 日立マクセル「MXSP-D240」
第2回 シャープ NetWalker「PC-Z1」
第1回 HTC「Touch Diamond」(090113)
 |
 |


このコーナーではプロダクトデザイナー秋田道夫氏による書評をお届けします。
毎回、秋田氏独自の視点でセレクトした、デザインにまつわる書籍の読後感を語っていただきます。お楽しみに。

 |
秋田道夫のブックレビュー
第21回
「思考の整理学」

・外山滋比古著
・筑摩書房/ちくま文庫(1986年4月刊)
・223ページ
・546円(税込み) |
●メタメタ書評
今回で21回目となるこのブックレビュー。読まれている方にどんな受け止められ方をしているのか気になるのですが、評論のプロでないわたしにとって大事なのは「プロダクトデザイナーの目線」を大切にすることかと思っています。
なぜこんな話を最初にしたかと言えば、それは「書評(ブックレビュー)」につながるような話がこの本に載っていたからです。
見たままに特徴が書かれたものは「第一次的情報」と呼ばれる。さらに見た目では分からない分析や分類が書かれた場合その文は「第二次的情報」になる。そういう行為を情報の“メタ(高い次元)”化という。そこからさらに抽象化が進むと「第三次的情報」になっていく。つまりどんどん見たままの情報が抽象化されていくわけでつまり“メタ・メタ”情報になるわけです。
ここからが面白い。
「(新聞の)社会面記事には興味をもって読む人も、社説はまるで勝手が違う。社説の読者が少ない。おもしろくないというのは、ほかの記事が第一次情報であるのに、これが(社説)メタ情報で、別の読み方を必要とするからである。」
笑っちゃったわけです。社説ならぬこの書評は、「抽象化」が進みすぎて本文からどうやってそう読み取れるのか分からないところまでいってしまうので読む人にとってはたぶん分かりにくいでしょうね。つまりメタメタなのです。
●捨てる技術
この本はすがすがしい。あたたかも暖房が効きすぎた部屋の窓を開けたときのような感じ、あるいはミント味の清涼菓子を食べたときのような感じ(メタ化)。
なぜそんなにさわやかかと言えば、頭の中で複雑にからみあった考えの糸を見事にほぐしてくれる効果があります。さらに進んでからんだ部分をすぱっと捨てて、端と端を直接つないだほうがよっぽどいいアイデアが浮かぶといったことが書かれてある。
例えばこんなふうに。
コンピュータが出現して、これまでずっと賢い人に求められていた知識のストック(倉庫)からいかにアイデアを生む工場として空間を残しておくかに重要なポイントが移るだろうと予言的に書かれてあります。
積み上げ型の思考方法では「第一次的情報」をよくできても、それを抽象化しメタ化するためには、工場を広くきれいな状態にしておかなくては「うまく動けない(アイデアが生まれない)」と解かれています。つまり人間の頭脳の役割は倉庫から工場に変わるというわけです。
講義や会議でノートを取るのも大事だが、それは要点にとどめて「聞くこと」に集中すべきであるとも書かれています。
思うにベストセラーとなる本には「誰でもが感じていることを、分かりやすく解説してあって、読後にあたかもその言葉を自分が考えついたかのような錯覚を覚える作用がある」と思っているのですが、まさにこの本はその定石に見事にはまっています。
分かっちゃいるけどなかなか「言葉」にはできない。
しかし、今の私たちにとってコンピュータがどうであるとかをすんなりと理解できますが、実はこの本が最初に登場したのが1983年、つまり27年前に書かれていたというのが驚きであるわけです。
●ブランドとしての知
すごく売れています。宣伝文には「100万部を突破」と書かれていますが、昨年の文庫本の売上の3位にもなったそうです。
これまでもコンスタントに売れていたのでしょうが、数年前にある書店の店員さんが「もっと若い時に読んでいれば…」というPOPを並べていた本の前につけたところ売れだして、出版社がそのキャッチコピーに目をつけて本の帯につけたところ全国的にも売れだしたそうです。
さらに大学の生協で売れて、東京大学や京都大学でも売れているということで、「東大・京大で一番読まれた本」と帯に入れたらこれが見事に読者の気持ちをつかんで現在のような状態になったそうです。
本の内容がいいというベースがあってのことですが、出版社の機転と、「知のブランド力」が働いているわけです。
●論文の価値
ただ読みやすく分かりやすいだけでは東大や京大はともかく学生がよく読む理由にはならないのですが、そこにひとつのキーワードがあります。それは「論文」という存在です。この本には論文にどう取り組むかについて大学教授という「現場」の人か書いたリアリティが作用しています。ずっと勉強を続けてきて先にふれた「知の倉庫」にいっぱい知識をためた学生たちが「知の工場」に変わる試練、それが「卒業論文」です。
その例としてエンジンを持った飛行機とエンジンを持たないグライダーを比較してその差を説明します。
「学校ではひっぱられるままに、どこにでもついていく従順さが尊重される。勝手に飛び上がったりするのは規律違反。たちまちチェックされる。やがてそれぞれにグライダーらしくなって卒業する。」
「何でも自由に自分の好きな事を書いてみよ、というのが論文である。グライダーは途方にくれる。」
「グライダー専業では安心していられないのは、コンピューターという飛び抜けて優秀なグライダー能力のもち主があらわれたからである。自分で翔べない人間はコンピューターに仕事をうばわれる。」
どうですか? どきっとしますね。
この本を読んでいてわたしはちょっとあることが気になってきました。
それは卒業論文というものにかけられた学生たちの膨大な「エネルギーの結晶」はその後どうなったのか? 美大で言えば「卒業制作」ですが、そこから実際の製品につながったものもあるかもしれない。同様に化学や数学や文学で書かれたものが、その後の成果を結んだものはないのか?
わたしは卒業制作で「学童用の椅子と机」作ったのですが、この本を読んでいてもう一度それを作り直して世に問うてみようかなと思い始めました。書くことも「メタ」ですが、やることも「メタ」です。まずは自ら実践。
30以上倉庫に眠っていたグライダーとも飛行機とも言いにくいその「試作品」に現代のエンジンを載せて飛べることを証明してみようかと。
●あの頃
タイトルが「デザインの整理学」としても通用すると思えるぐらいにデザインを考えることと共通する話が数多く載っていて、デザイナーにも是非読んでほしい1冊だと思います。
本が登場した1983年頃はどういう時代だったのか自分なりに思い出すと、とても「しあわせな時代」だったように思います。1984年には日経平均株価が、はじめて10,000円台を突破したということで、そこからバブルがはじける1990年代までずっと右肩上がりの状態だったと言えるでしょう。すこぶる良いという実感はないけれどなんだか「これから良くなりそうな」そういう空気が支配していました。
あの頃就職も順調でしたし、夏はテニス、冬はスキーと「余暇」を楽しんでいました。今で言うクラブの「マハラジャ」が東京に出現したのも1984年です。
たいへんな時代に学生生活を送った外山先生は、そんな浮かれた学生(社会全体)に「油断」を感じていたんでしょうね。今にしてみれば的を射た話も発売された当時どこまで理解できたのか。
先日テレビを観ていたら、大学生への月々の仕送りの金額が1984年のレベルに戻った話をしていました。くしくも日経平均株価は10,000円を前後しています。この本が生まれた時代にベクトルは違えど戻ったわけです。
●ほんものを生み出すヒント
最後にもうひとつデザイナーとしてもドキッとするエピソードを紹介して終わります。
「島田清次郎は大正の文学青年から見て、まさに天才だった。それを疑うものは少なかった。それがどうだろう。僅か60年にして、ほぼ、完全に忘れられてしまった。むしろ、夏目漱石の文学について疑問をいだくものが多かった。批判もすくなくなかった。それがいまでは国民文学として、近代文学において比肩するものなしと言われるまでになっている。」
「時の試練とは、時間のもつ風化作用をくぐるという事である。」
「思考の整理には忘却がもっとも有効である。(中略)忘れ上手になって自然忘却の何倍ものテンポで忘れる。」
うーん。
ほんものとはなにか。時代を乗り越えるデザインとはなにか。今の時代にあって「先に残るもの」を考える(生み出す)にはどうすればいいのか。まず多くのものを知る、そしてそれをものすごい勢いで「忘れる」。そのことによって時間を何倍ものスピードで「先回りできる」。そんなことを一度も考えたことがありませんでした。
思考の整理とは、いかにうまく忘れるかである。
なんともすごい言葉にぶつかってしまった。

|
|