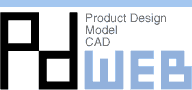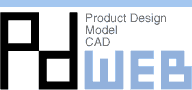pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン
●今、気になるプロダクト
その30:モジュールを組み合わせてモノを作る「LittleBits Synth Kit」
その29:水縞「全国架空書店ブックカバー」をめぐって
その28:ESPのGrassroots ピックガードギター「GR-PGG」が面白い
その27:米ナッシュビルのハンメイドギターピック「V-PICKS」
その26:キリンビバレッジ「世界のkitchenから」をめぐって
その25:「UP by JAWBONE」をめぐって
その24:「未来の普通」を実現したツール、Livescribe「wifiスマートペン」
その23:スマホでは撮れない「写真」を撮るためのコンデジ「EX-FC300S」
その22:真剣に作られた子供用ギターは、ちゃんとした楽器になっている「The Loog Guitar」
その21:紙をハードウェアとして活かしたデジタル時代の紙製品
その20:Kindle paperwhite、Nexus 7、iPad miniを読書環境として試用する
その19:未来の形を提示したヘッドフォン、Parrot「Zik」を考察する
その18:iPadなどタブレット用のスタイラスペン3タイプ
その17:カプセル式のコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」
その16:iPadで使うユニークなキーボード、3種
その15:紙のノートと併用できるオーソドキシーのiPad用革ケース
その14:今世界一売れているボードゲーム「エクリプス」に見るインターフェイスデザイン
その13:SimplismのiPhoneカバー「次元」シリーズ
その12:3,000点の展示数は当然だと感じられる「大友克洋GENGA展」
その11:大人が使って違和感のない文具、「Pencoのディズニーシリーズ」の魅力の秘密に迫る
その10:VOXのトラベルギター「APACHE」シリーズをめぐって
その9:業務用スキャナのScanSnapモードを試す
その8:シリーズ「iPhoneに付けるモノ」:iPhoneの録音周りを強化する
その7:フルキーボード搭載の新ポメラ、キングジム「DM100」
その6:取材用ノートケース製作録
その5:40年間変わらないカップヌードルというモノ
その4:インターネット利用のモノ作り「Quirky」の製品群
その3:最近の保温保冷水筒をチェック
その2:「スーパークラシック」と「スーパーコンシューマー」の文具たち
その1:五十音「Brave Brown Bag」
Media View
●秋田道夫のブックレビュー
第22回:「だれが決めたの? 社会の不思議」
第21回:「思考の整理学」
第20回:「デザインの輪郭」
第19回:「デザインのたくらみ」
第18回:「覇者の驕り―自動車・男たちの産業史(上・下)」
第17回:「素晴らしき日本野球」
第16回:「建築家 林昌二毒本」
第15回:「ブランディング22の法則」
第14回:「中国古典の知恵に学ぶ 菜根譚」
第13回:「プロダクトデザインの思想 Vol.1」
第12回:「先生はえらい」
番外編:「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
第11回:「知をみがく言葉 レオナルド・ダ・ヴィンチ」
第10回:「ハーマン・ミラー物語」
第9回:「ポール・ランド、デザインの授業」
第8回:「プロフェッショナルの原点」
第7回:「亀倉雄策 YUSAKU KAMEKURA 1915-1997」
第6回:「I・M・ペイ―次世代におくるメッセージ」
第5回:「ル・コルビュジエの勇気ある住宅」
第4回:「芸術としてのデザイン」
第3回:「天童木工」
第2回:「アキッレ・カスティリオーニ 自由の探求としてのデザイン」
第1回:「柳宗理 エッセイ」
Tool View
●魅惑のレンダリングワールド
第6回:Maxwell Renderを用いた小坂流ビジュアル術
第5回:Maxwell Renderの概要
第4回:nStyler2.1をより使い込む
第3回:さらにパワーアップしたnStyler2.1
第2回:Hayabusaのレンダリング画像
第1回:Hayabusaの概要
●[集中連載]SolidWorks 2008レビュー!全4回
最終回:「フォトリアルなレンダリング画像を作る」
第3回:「レイアウト」検討からの部品作成
第2回:サーフェス上スプラインとソリッドスイープ
第1回:インターフェイスやモデリングの概要
LifeStyle Design View
●さまざまな日用品
第1回:空想生活「ウインドーラジエーター」
●IHクッキングヒーター
第3回:「MA Design」
第2回:「空想生活COMPACT IH」
第1回:「東芝MR-B20」
●オーディオ
第3回:「TEAC LP-R400」
第2回:「amadana AD-203」
第1回:「JBL spot & Jspyro」
●ライト
第5回:「BIOLITE EON」
第4回:「TIZIO 35」
第3回:「ITIS」
第2回:「Highwire 1100」
第1回:「Leaf light」
●トースター
第4回:「ZUTTO」
第3回:「VICEVERSA」
第2回:「±0」
第1回:「Russell Hobbs」
●コーヒーメーカー
第6回:「±0」
第5回:「MA Design」
第4回:「ZUTTO」
第3回:「deviceSTYLE」
第2回:「Rowenta」
第1回:「Wilfa」
●ハードウェア
第3回 日立マクセル「MXSP-D240」
第2回 シャープ NetWalker「PC-Z1」
第1回 HTC「Touch Diamond」(090113)
 |
 |


このコーナーではプロダクトデザイナー秋田道夫氏による書評をお届けします。
毎回、秋田氏独自の視点でセレクトした、デザインにまつわる書籍の読後感を語っていただきます。お楽しみに。
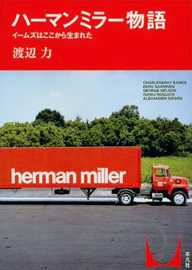
 |
秋田道夫のブックレビュー
第10回
「ハーマン・ミラー物語」

・渡辺 力(著)
・ 平凡社(2003年11月刊)
・221ページ
・2,520円(税込み) |
|
 |
●出会えたよろこび
「名著である」
人生においてもデザイナーとしても大先輩である渡辺力さんの書かれたものをそういうのはまことに僭越なのですが、そう表現するのがもっとも適切な気がします。
この本には、優れた映画を観たときに感じる「終わってほしくない、ずっと見続けていたい」。そういう思いと通じる感覚があるのです。
筆者である渡辺力さんは1911年生まれ。現在97歳の「現役デザイナー」であります。渡辺さんは1936年東京高等工芸学校(現在の千葉大学)を卒業、後に母校での教鞭をとられるなど教育に関わられた後1949年に独立、1952年には日本インダストリアルデザイナー協会の設立に関わられ、理事に就任されていました。
多くのインテリアや家具のデザインを手がけられ、最近でも腕時計や置時計の新作を発表するなど年齢を感じさせないその情熱に驚かされます。
それらの作品は端正でプロポーションに優れたデザインですが、ただシンプルなだけではなくしゃれっ気を感じさせるものがあります。
そんなしゃれっ気が本中の文にもさりげなく現われています。ちなみにこの本のタイトルも有名な音楽映画「グレン・ミラー物語」とかけたものです。
デザイン界の巨匠であるにもかかわらず、きわめて平易で読みやすく自分を黒子に徹して書かれているところだけをとっても感心をしてしまうのですが、それは本文中にも触れられていますが、ご自身が建築雑誌「新建築」の編集をされていた経験があり、編集者としてのキャリアが、客観的で読みやすい文を書かれるベースになっているのだと思います。
●企業の分かれ道
この本の主人公は、戦前から戦後そして今に至るまでずっと良質で高いデザイン性をそなえた家具や事務用品を作り続けているアメリカの家具製造販売メーカーであるハーマン・ミラー社とそこで活躍した有名なデザイナー達です。
最近でいえば座る人に細かいアジャスト(調整)が可能な、長く座っていても疲れない事務椅子の決定版として有名なアーロン・チェアーを作っているメーカーといった方が分かりやすいかもしれません。
ハーマン・ミラー社は、1923年にミシガン州にある小さな町ジーランドという場所で生まれました。全米の中でも有数の家具工業の盛んな土地です。そこにあった家具会社をハーマン・ミラーらのグループが買収し、高級なドレッサーを製造しはじめたのです。
今でも、1929年にアメリカのウオール街から始まった世界恐慌の話を知る人は多いのでしょうが、実はその直前まで空前の好況状態にアメリカがあったことを知る人は少ない。
第一次世界大戦で、戦勝国となったアメリカは、戦争の終わった1918年から大恐慌の起きる1929年までの10年間、モノは作れば売れるし、賃金はどんどん上がるという好循環が繰り返されていました。今でいえばバブル状態だったわけです。
ハーマン・ミラー社もご多分にもれず、高級な家具であってもどんどん売れて会社の規模も順調に拡大していきました。そして訪れた大恐慌の前に、倒産の瀬戸際まで追い込まれたのです。
その危機的状況にあったときに下した会社の判断によって、今でも世界的に有名なメーカーとして生き残ることができたわけです。
ここから先は本を手に取った皆さんの楽しみとしておきましょう。
●デザイナー列伝
本の副題にも「イームズはここから生まれた」と書かれているように、登場する有名な多くのデザイナーの中でもチャールズ・イームズについて、多くのページを割いて書かれています。
ハーマン・ミラー社とイームズの組み合わせによって、量産性と耐久性に優れユーザーが求めやすい製品を多くの種類(40種類)大量に世に送り出すことができました。
現在でも当時の製品がオークションやショップに並んでいますが、1950年代の初頭に生まれた製品が現在でも壊れることなく使うことができる製品が多く存在するのは考えてみるととても稀有なことだと思います。同時に50年以上前の製品ですが、今でもまったく古く感じないどころか、ますます輝きを増しているとさえ思えるデザインであるのはまったく驚異的なことです。
そのイームズやイサム・ノグチについての詳細なエピソードの数々は、いきいきとして興味深いものばかりです。しかし、わたしが分けてもひきつけられたのが、ジョージ・ネルソンと彫刻家のブランクーシに関する記述でした。
ジョージ・ネルソンの家具で有名なのは、円筒のクッションを並べた「マシュマロソファー」と円錐をカットした形状をした「ココナッツチェアー」、そしてユニークな形のさまざまな掛け時計が挙げられますが、イームズに比べるとそう多くの製品があるわけではありません。
わたしのこれまでのネルソンに対する認識もそういうものをベースにしたものであったのですが、この本で知ったジョージ・ネルソンはデザイナーとしてだけでなく優れた評論家であり、なによりずば抜けた世の中に対する見識と先見性をもった思想家であったことを知ったのです。
不況下で下したトップの判断が、会社を存続に導いたことが、最初の大きなステップアップだとすれば、次の大きなステップは、間違いなくこのジョージ・ネルソンとハーマン・ミラー社との出会いにありました。この出会いによってデザイン性で世界に知られる今のハーマン・ミラー社の形が出来上がったのだと思います。
●バトンを引き継ぐ
ジョージ・ネルソンは、ハーマン・ミラー社の仕事を独占しないで、チャールズ・イームズを会社にひき合わせています。他のデザイナーをハーマン・ミラー社に紹介すれば、当然、彼の仕事量と、社内でのデザイナーとしての重要さが目減りすることを知りながら。ネルソン曰く「とにかく、有能な人が必要です。もし万一私がよいデザイナーでないとしたら、その時こそ、その必然性が分かりますよ。そしてまた、私がすべてのいいアイデアを持っているはずもありませんしね」。
しかし彼のこの言葉が、ハーマン・ミラー社での評価を上げることになったのは言うまでもありません。
わたしはこの話を紹介できることをとてもうれしく思うのです。そしてこのエピソードに限らず優れたデザイナーの多くの知られていないお話に満ちたこの本を紹介し、1人でも多くの人に読んでいただくお手伝いをすることが使命であるかのように感じています。
文筆業でもない渡辺さんがどうしてこの本を書くことになったのか、そのいきさつを紹介して最後とします。
「これは私自身が編集部に持ち込んだ企画でした。
中略
そういう行動に出たのは、ハーマン・ミラーの家具を百貨店の子会社が輸入をしはじめたことにありました。
驚いたことに、デザイン史上稀にみる革新的な仕事をしたハーマン・ミラーのことも、ネルソンやイームズのこともそこから多くのことを学ぶべき立場にある家具メーカーが、あまりに知らないばかりか、新素材を使った現物を目の当たりにしてもあまり関心を抱かなかったのです。
中略
それを知らないばかりか、知ろうとしない日本のメーカーを触発したい、啓蒙したい。今、振り返るとなんとも生意気な物言いですが、当時の私には、そういった一種の義憤にも似た思いがあったのです」。
この連載が雑誌「室内」に掲載をはじめられたのが、1976年。それから30年経った今も、メーカーだけでなくわたしを含め多くのデザインに関わるものにとっても警鐘といえる言葉です。
さいわいデザインは、知れば知る程奥深くなにより「たのしい」のです。そしてこの本も読んでいてとてもすがすがしく「たのしい」のです。
ぜひ読んで渡辺力さんのメッセージのバトンがさらに若い人に引き継がれることを願いながら結びたいと思います。

|
|