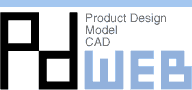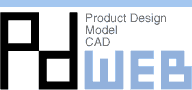●3Dプリンタのすべて
本編へ
●新世代デザイナーのグランドデザイン
第2回:中川政七商店
|page01|page02|
第1回:TENT
|page01|page02|
●素材とデザイン
第8回:AZiS
|page01|page02|
第7回:益基樹脂/mass item
|page01|page02|
第6回:吉田カバン
|page01|page02|
第5回:能作
|page01|page02|
第4回:山田平安堂
|page01|page02|
第3回:FACTRON
|page01|page02|
第2回:Hacoa
|page01|page02|
第1回:かみの工作所/TERADA MOKEI
|page01|page02|
●女性デザイナーによる最新プロダクト大集合! [インテリア/テーブルウェア編]
本編へ
●最新デザインツールのすべて[2013 Spring]
本編へ
●Special Talk in Summer
小牟田啓博、デザインプロデューサーの仕事を語る
|page01|page02|
暑い夏に熱く語る! 真夏の夜の男子会
|page01|page02|
●pdweb座談会 モデル造形の可能性を考える
|page01|page02|
●3Dプリンタ特選ガイド
本編へ
●特選デジタルツール2011「我が社の一押し最新デザインツール」
Zコーポレーション/スリーディー・システムズ・ジャパン/アプリクラフト/スペースクレイム/豊通マシナリー
●プロダクトデザイナーのためのCAE活用術
part1 デザイナーのためのCAE概論
part2 最新製品ガイド
●特選デジタルツール2010「我が社の一押し最新デザインツール」
part1 概論:より効果的なプレゼンを行うための最新ツール使いこなし
part2 最新製品ガイド
●新世代デザイナーたちのモノ作り
第6回:シラスノリユキ/color
| page_01 | page_02 |
第5回:福間祥乃/PRIMITIVE MODERN
| page_01 | page_02 |
第4回:参
| page_01 | page_02 |
第3回:MicroWorks/海山俊亮
| page_01 | page_02 |
第2回:NOSIGNER
| page_01 | page_02 |
第1回:田川欣哉/takram
| page_01 | page_02 |
●新春スペシャル対談「デザインディケイド2010」
| page_01 | page_02 |
●特選デジタルツール2010「我が社の一押し最新デザインツール」
part1 スリー・ディー・エス/サイバネットシステム/ボーンデジタル/アプリクラフト/グラフィックプロダクツ/マクソンコンピュータ
part2 オートデスク/ソリッドワークス・ジャパン
●これが人気プロダクトの生産現場だ!
Part5
陶磁器に新しい命を吹き込むモノ作りの妙「セラミック・ジャパン」
(愛知県瀬戸市)
| page_01 | page_02 |
Part4
プライウッドによる自在なデザインが魅力のインテリア「天童木工」
(山形県天童市)
| page_01 | page_02 |
Part3
高岡銅器の伝統が生きるフラワーベース「ASIWAI」
(富山県高岡市美幸町)
| page_01 | page_02 |
Part2
古くて新しい、ガラス製品の加工現場に迫る
菅原工芸硝子(千葉県山武郡九十九里町)
| page_01 | page_02 |
Part1
秋田道夫デザインの文具Primarioシリーズを作る
「takeda design project」(新潟県燕三条)
| page_01 | page_02 |
●次世代デザイナーズFILE
| 1980年生以降まれのデザイナー |
| 1975〜1979年生まれのデザイナー |
| 1970〜1974年生まれのデザイナー その2 |
| 1970〜1974年生まれのデザイナー その1 |
●新春スペシャル対談:今、デザインを取り巻く環境
| page_01 | page_02 |
●デジタルデザイン最新ツールガイド
・Part7 Peripherals
・Part6 WS(ワークステーション)
・Part5 RP/3Dプリンタ
・Part4 CAE/CAM
・Part3 2D CG/2D CAD
・Part2 3D CAD/3D CG(レンダリング系)
・Part1 3D CAD/3D CG(モデリング系)
●デザイン家電の匠たち
・Part5 深澤直人氏デザインの「±0」シリーズ
・Part4 柴田文江デザインの「象印ZUTTOシリーズ」
| Chapter01 堀本光則氏 | Chapter02 柴田文江氏 |
・Part3 鄭秀和
| page_01 | page_02 |
・Part2 村田智明
| page_01 | page_02 |
・Part1 秋田道夫
| page_01 | page_02 |
●デザイナーのためのモデル制作の最先端
・Part 5 さまざまなモデル出力機の特徴を知る
・Part 4 モデル制作関連のサービスビューロー一覧
・Part 3 モデル出力機、その仕組みと種類
・Part 2 モデルの入力と編集のためのシステム
・Part 1 はじめに
●理想のモデリングツールを考える
・Part 3 デジタルデザインの課題
・Part 2 カタチ作りとインターフェイス
・Part 1 デザイナーとCAD、バトルの歴史
 |
 |


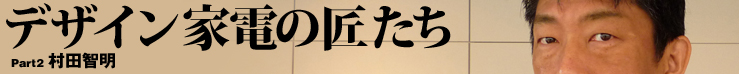
|


東京・五反田のMETAPHYSショールームにて村田智明氏に話を聞いた




五反田の東京デザインセンターにあるMETAPHYSの東京ショールーム |
 |
デザイナー村田智明氏が牽引するデザイン家電「METAPHYS」は、複数の中小企業コンソシアムから成り立つブランドだ。さまざまな中小企業の持つコアテクノロジーを見極め、村田氏はそれにデザインと販路を与える。実際、METAPHYSはデザイン家電に留まらず、インテリア、自然・エコロジー、ステーショナリー、ファッション、アミューズメントと広範な展開をしている。行為のデザイン、アンチテーゼ、タイムレス、ミニマリズム、、、METAPHYSを語ることは同時に、村田氏のデザイン哲学を語ることでもある。
●デザイン家電とは何?
−−まず、村田さんは「デザイン家電」をどのように捉えていますか。
デザイン家電と量販店の家電、どう違うのかという質問はよく聞かれます。マーケティング的に言えばまず販路が違う。デザイン家電は基本的には1つの商品を長く売っていこうという思想ですので、当然量販店とはチャネルが違う。量販店は大量に買い付けて、できるだけディスカウントしながら提供して、そして大体半年から1年で売り切りというかたちですから、販売スタイルが違いますね。
デザイン家電は、ライフスタイルショップやインテリアショップを中心に売っていきます。その商品が置かれている空間をお客さんにイメージさせながら、その商品の持つ魅力を最大限に引き出そうとする。そうして、育て、それを長く売っていこうという思想ですね。したがって、量販店向けの製品よりもう少し空間を意識したフォルムや色が求められます。スペック的にはインテリアショップのユーザーターゲットに近いものということで、ファミリーよりシングルを意識したものになってきます。
ただ、今後はファミリー層までインテリアは広がりつつあるということでこれからのデザイン家電はファミリールックスなモノもだいぶ増えてくるでしょう。amadanaが大きな冷蔵庫を出しているように、そろそろそっちへも広がるだろうと見ています。
−−METAPHYSは量販店に置く気はないのですか。量販店に置いているデザイン家電もありますよね。
そういうデザイン家電もあります。独禁法の問題とかも関わってくる問題なんですが。例えば、あるインテリアショップで10,000円の価格で売っている商品が、ある家電量販店では8,800円、しかもポイント還元がついている。そうなると、ライフスタイルショップは単なるショールームとなり、売れないという状態をつくりだすことになって、販売をやめると思うんですね。そういう問題をはらんでいますので、今量販店で売られているものはポイント還元分を除けば、インテリアショップ系と値段がほぼ一緒だと思います。
この流通形態は、METAPHYSでは認めていないんです。さっき言ったようにマーケティングのスタイルが違いますので、小さなインテリアショップやライフスタイルショップが空間提案しているのを応援し、一緒にブランド構築していきたいのです。
例えば今回2008アンビエンテ(フランクフルトで開催される世界最大の消費財見本市)に出展しました。ミラノサローネで発表し、ロンドンの100%デザインに出店し、そして今回。そこから学んだことなんですが、ヨーロッパの人たちは、初めに出たものに対して「面白いね」「すごいね」とは言うんですけど、絶対購入しないんです。2年目も出して、3年目も出して、継続して出していることを確認すると「そろそろ買おう」となります。
−−3年我慢しろと(笑)。
と言われています。例えば電子キャンドルの「hono」も2年経ちますので、メディアへの露出度や認知度が高く、これはマーケットに受け入れられていると判断されるのです。アワード実績も買い付けへのギャランティになっていると思います。ということで、今回のアンビエンテでは、買いがものすごく発生したのでびっくりしたんです。バウハウスミュージアムだったりサンフランシスコのモダンアートミュージアムだったり、ミュージアム系もたくさんきました。
マーケットの作り方で日本と大きく違うのは、日本は新製品を出すと、「まず新製品はうちに回せ」となりますが、ヨーロッパでは「新製品はいらない」(笑)。すごくそれを感じました。
例えば、TMP PAPER COLLECTORというスチールワイヤーの新聞受けがあるんです。Willi Glaeser というデザイナーが1989年に発表したものですが、その1品をずっと売り続けているスイスのディストリビューターとお会いしました。その1つのブランド商品を何十年と売っているわけです。それにはびっくりしました。そういうタイムレス商品ばかりをいろいろコレクションしているディストリビューターなんです。ヤコブセンの椅子とかと同じですよね。今回外から眺めて、ブランドを育てる流通サイドの文化が日本にはないことを実感しました。この屈折した流れに一石を投じるのがデザイン家電の1つの側面、役割ではないかと思います。
だから今METAPHYSが目指しているのは名作を作っていくこと。10年以上販売できるような名作を。例えばテープカッターでも今年で終わりだよねというようなデザインはしていないつもりです。だから、作ったものが爆発的には売れないけれど、ずっと10年売れる。
−−それは時間に消費されないというか、価値観が時間に対してもちゃんと勝ち抜いていけるような、消耗されないという意味ですよね。
先ほどのスイスのディストリビューターは「タイムレスデザイン」と言っていました。いい言葉だと思います。
−−「タイムレスデザイン」は概念的には分かりますが、時代はどんどん変わっていきますよね。
家電は難しいですね。
−−機能・性能面の進化もありますし。
家電のタイムレスデザインを実験的に取り組むような例があります。僕は実行委員長として、今年1月26日にエコプロダクツコンペ2007の作品展示発表会を行いました。審査員も喜多俊之さん、山本良一さん、池上俊郎さん、益田文和さん、佐合ひとみさん、間宮吉彦さんにお願いしました。その中で大賞を取ったのが、エプソンのプリンタだったんです。テーマ企業のコンペ課題を、企業側と調整して作ったんですけど、コンペの課題は家電の抱える短期的な消費行動に対する、ライフサイクルアセスメントのイノベーティブな提案が必要であるとしました。中身をどんどんバージョンアップさせて、外側は漆器でも竹の集成材でもいいじゃないかと。そういうデザインが出てくるようなテーマにしましょうとエプソンと話し合った。パソコンにつなげばソフト的にバージョンアップするし、機能もそのパーツだけを入れ替える。そういう可能性を提供しました。
やはりこれからの家電製品は、中身がダメになったら外身は捨てるという従来の考え方からシフトすれば、例えば今言ったようにパソコンからダウンロードしてアップグレードしていけるようなものもできていくんじゃないかなと。「タイムレス」という考え方でもう1回プロダクトをリコンストラクトすること。これが僕の考える「デザイン家電のあり方」です。
−−METAPHYSが販売先として目指しているのは日本市場だけではなく、ヨーロッパ、アジア、欧米などワールドワイドな展開ですか。
去年の12月からソウルで、METAPHYS.KR(韓国版 WEB store)というサイトを立ち上げて販売を始めたんです。アメリカはMoMAともう1つの販売チャンネルでスタートしました。ヨーロッパもスイスから始まります。
●METAPHYS誕生の経緯
−−そもそもMETAPHYSはどのように誕生したのでしょうか。
METAPHYSは「デザイン業とは何か」の答えとして生まれたような気がします。僕はプロダクトデザインのデザイン事務所を21年ほどやっていて、それでも何かしっくりこない感覚を抱いていました。ある時、自分が属する職業分類を探したときに、「その他」という職業だと。
−−デザイン事務所は「その他」ですか。
「我々はその他です」と(笑)。デザイナーとかプロデューサーとかコンサルティングに当たる人は全部「その他」。でも我々は「サービス業」に入るんですよ。「そうか、サービスだったのか」と気づいたときに、じゃ本当にサービスができているのかと正直疑問に思いました。
例えばA案、B案、C案とスケッチを描いてプレゼンして、先方が選びます。選ぶときに企画が「A案のアイデアもちょっと入れてよ」と言われる。エンジニアが「コストを下げたいので共通部品を使ってくれ」という。そこに上司がやってきて「色は売れ筋を参考にもうちょっとこうしてほしい」。要は我々は言いなり型になっているんです。でも、その通り作っても売れない、あるいは、販売店の評判がよくないという結果が。商品化する率は非常に低かったわけですね。
そして仕事の入り口も、電話がかかってくるのを待っている待ちの姿勢です。そういう自分に嫌気がさしました。
じゃあ本当のデザイン業界のサービスとは何なのかが、大きなテーマになってきました。例えばある中小企業は、自社商品ブランドを持たず、最終製品の流通販路も持っていない。当然、企画やデザイン部署も持っていない。そういうケースでは彼らができないエリアのコアコンピタンスを我々が全部もってやればいいんじゃないか。それがデザインをするということではないかと。
アジアの台頭の中を生き抜いてきた中小企業は、1社1社「おおっ」という技術を持っているけどそれが生かされていない。企業や流通の都合で曲げられ、本来のあるべき商品の姿から遠いところにいってしまう企画に対して、「No」と言わないといけない。今までのように言われたことをすることが本当に正しいことかと考え始めたんです。
そもそも、その商品を出す意義があるのかどうか。地球資源を使って、量産し、世の中にどんな効果を残そうとしているのか。バックキャスティングという方法でこれからずっと先にあるべき姿を予見し、そこからプロダクツの倫理を組み立てなければ、CSR(企業の社会責任)が成り立たない。また、ブランディング、デザインがきちんと生きるステージをこちらから用意してあげることで、初めて理想のデザインが実現できることも我々は理解しておかなければいけない。「ドラッグストア、ホームセンター、ディスカウントストア、量販店では意図するデザインが実現しない」ということの交換条件を、ちゃんと提示してメリットや損益を示す必要があるということ。それは我々デザイン会社が今まで責任をもたなかったところです。我々が責任をもって販路も作っていくということは非常に重要なことで、簡単に言えば「責任付きデザイン」です。
−−「コンサルティングと販路付き責任デザイン」ですね。それは今までの中小企業さんとのお付き合いの中で、村田さんの意識改革があったから変わったのですよね。
バカでしたね、長いこと(笑)。
−−中小企業さんはメーカーとしてモノは作れるけれども、市場が見えていないとか、自分の持ち味を客観視できていないところがあったのでしょうか。
そうなんですね。ですから「コンピタンス・ヒアリング」といってまずは企業の優位性競争力のヒアリングをするし、扱っている材料や加工技術などいろいろなものを見せてもらいます。また、ファブレスでも調達能力やアウトソーシング能力もコアコンピタンスに入ります。「これは」というものは僕らの方が見る目があると思うんですよ。一番ユーザーに近いところにいますから。メーカーとユーザーのちょうど間にいて、それを目利きする立場にあるので。
だから我々から目利きの力を奪ってしまう今までの発注の仕方は間違っていると思うんですよ。中小企業が完全に企画から全部やってしまって、「これに形を付けてください」という部分発注のやり方は実は間違っていたのです。
−−村田さんのデザインはMETAPHYS以前と以降で変わりましたか。METAPHYSとしてのデザインというものがあるのでしょうか。
僕のテイスト。あまりないと思いますよ。ないというとおかしいんですけど、METAPHYSに関しては「ミニマリズム」というのは全部守っています。虚飾はしないですね。
−−何が聞きたかったのかというと、村田さんはMETAPHYSらしさをどこにポイントを置いているのかなと思ったのです。ミニマリズムというのは何にでも言えますよね。
いい質問ですね。1つは、内在するデザインです。「something inside」と言っていますけど、何かそこにある。それは形ではないものを村田がデザインしているところなんですよ。例えば「hono」も、意匠権を取れないようなシンプルな円柱形ですよね(意匠権利化済み)。でもそこには形からは見えないギミックがあったり、使う人をアフォードしていく時間軸のデザインができているのです。それを僕は「行為のデザイン」と言っています。
結局デザインの需要な要素の1つは「感動」だと思っているんです。感動がないもの、また、今までの形の踏襲で性能だけが上がったものや色替えだけだったり。そういうものをGマークの審査ではあまり評価していません。だから去年通ったのに何で今年は落ちたのかというと、「感動」がなくなっているから。ただ安全で使いやすいものがいいとは思わないですね。だからある種の感動をタイムレスに維持できる商品を作り出すこと。これは非常に難しいことですけど、これをMETAPHYSの中に入れているわけです。something insideですね。
−−それはすごく難しい作業ですよね。時間に消費されないものを作りたいと思って作られているデザイナーさんはたくさんいらっしゃると思います。
すみません(笑)。
[次ページへ]
|
|