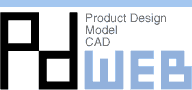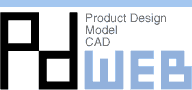今回からpdwebの特集新シリーズ「新世代デザイナーたちのモノ作り」をスタートします。第1弾は東京・新宿御苑にオフィスを構えるデザインエンジニアリングファーム、takram代表の田川欣哉氏。デザインとエンジアリングを1つに捉える彼のスタンスは、斬新でありながら古くからの職人のあり方も思い起こさせるものだ。takramは、モノ作りのシステムそのもののリスタートを企んでいるのかもしれない。
田川欣哉(たがわ きんや)
1976年東京生まれ。1999年東京大学工学部機械情報工学科卒業。2001年Royal Colledge of Art修士課程修了。2001年よりリーディング・エッジ・デザインへ参加。2006年takram設立。デザインとエンジニアリングの2つの視点を生かした多角的なアプローチを得意とし、インタラクティブなアート作品からソフトウェア、ハードウェアまで幅広い製品を手掛ける。2007年Microsoft Innovation Award 最優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞多数。
http://www.takram.com |
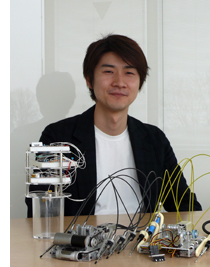 |
●takram設立までの経緯と目的
−−ではまず、takram設立の経緯、概要をお話いただけますか。
僕は東大の機械科出身ですが、takramは卒業後7、8年を経て、同級生だった畑中元秀と一緒に設立しました。畑中とは卒業後は別の道を歩んでいて、また合流したかたちですね。
そもそも僕は、大学の工学部にいけばモノ作りができるものだと思っていたんです。でも、あるメーカーにインターンにいって現場を見ていたら、そこにはプランナーやデザイナーと呼ばれる方がいて、エンジニアは技術面のリアライゼーション担当みたいな感じでした。何を作ればいいのかという話は、プランナーやデザイナーの仕事で、それが僕にとってはとても意外だったんです。僕は、当然その部分もエンジニアがやるもんだと思い込んでいて、それができるからこそ工学部にいこうと思っていたから。単純に僕の社会勉強不足だったんですけど(笑)、そういった現実に当時かなりショックを受けました。
その後山中俊治さんの事務所にお世話になって、デザインとエンジニアリングの両方に関わる仕事を濃密にやらせていただきました。そこで修行を積んだ後、独立しようかなと考えていたタイミングでちょうど畑中と再会したのです。
当時、畑中はスタンフォード大学にいたのですが、ひょんなきっかけから連絡を取り合うようになりました。何回かやり取りするうちに、目指している方向が近いので一緒にやれるかもしれないなということになりました。
−−お二人とも今の企業のモノ作りの状況に対して、分業化されていることに否定的な印象をお持ちだったのですね。
分業化については、歴史的にいろいろな理由があってそうなっているので、それ自体を否定するつもりは全然ありません。僕らは、コンセプトを考える部分とそれを現実化していく部分の両方にまんべんなく関わりたいと思っていて、そういう理想を実現するためのスタイルを自分たちでゼロから考えてみてもいいかなというのが、takram設立の目的になっています。
−−なるほど。田川さんと中畑さんの方向性が合致して会社設立となった。活動内容といいますか、ビジネスモデルはどのように考えましたか。
基本的にはクライアント企業に対するデザインと設計の提案です。僕らはエンジニアさんとはエンジニアリングの言葉で話をして、デザイナーさんとはデザインの言葉で話ができるという、バイリンガルな点が特徴になっていると思っています。僕らだけで作ることもあるのですが、大きなプロジェクトではたいてい多くの人が関わるので、そういった場合、takramは取りまとめの役割を担うことも多いです。いろいろな方たちの意見を聞いて、それを1つにまとめていくような役割ですね。その過程で僕らがエンジニアリングの言語とデザインの言語の両方をしゃべっている感じです。
そしてプロトタイプを作りながら試作を繰り返していきます。問題が複雑でこんがらがっていても、少しずつ進んでいけばそのうちゴールにたどり着く、というようなやり方なんですけどね。クライアント企業にはデザイナーもエンジニアもいらっしゃいますけれど、そこに僕らが入ることで、今までと違ったモノ作りの進め方ができるんじゃないか、というのが僕らの考え方であり仕事です。
−−takramの役割というのはコンサルティングに似ているのかもしれません。ビジネスの実態はどこにあるのでしょうか。
僕らはプロトタイプをどんどん出していき、そこにクライアントも含めてチーム全員のアイデアを集約をしていきます。当然、個別の要素をそのままごった煮にしてもまとまらないので、複数のアイデアを1つのアイデアにまとめたり、別々のニーズを満たす第3のアイデアを提示して、こういった案もありますよ、といった動き方もします。その過程で、どんどんプロトタイプを作り、みなさんに見てもらってまた議論をします。
また、テーマに即してこちらからデザイン案を提案するという普通のデザイナー的な役割もありますし、純粋にエンジニアリングのお手伝いをするというやり方もあります。
−−それはクライアント企業の状況次第ですね。
そうですね。逆に言うと僕らは、「こういう役割しかありません」という定型をあまり作らないようにしています。エンジニア的に振る舞ってほしいクライアントさんであれば僕らはエンジニアリング寄りの発言を多くしますし、ピュアにデザイナーとして入ってほしいというときにはデザイナーとして入る。ただ、僕らが一番自分たちの能力がうまく出るなと思っているのは、両方を重ねてアウトプットを求められているとき。そのほうがパフォーマンスは高いと思っています。
−−takramさんに依頼するクライアント企業には、もちろんインハウスのデザイナーやエンジニアがいると思います。しかし発想などが煮詰まってしまって、外の風が欲しいという状況になっているからtakramに依頼がくるという流れなのでしょうか。
それもいろいろですよね。煮詰まっている場合か、自分たちだけではテーマが難しすぎるかなと思われるときに、「takramの活動を雑誌を読んだことがある」とか「興味を持っていたから」というようなことからアプローチしていただく場合が多いです。
たいていの場合、僕らは外から入ってくるプロジェクトに対しては、ある意味素人なんですよね。クライアントの会社には、そのテーマに10年以上関わっている方々もいらっしゃって、そういう方からどれだけたくさん経験や知識を僕らのほうに引き出せるかどうかがとても重要です。そのために僕らはプロトタイプをどんどんと出していく。そうすると専門家からいろいろな意見が出てきて、「なるほど、そこが設計のポイントか」と理解が進みます。逆に、どれだけ彼らが今までやってきたことに固執しているか、方向が狭くなっているかといったネガティブな点も浮き彫りになっていきます。
彼らの問題意識とか今までのスタイルを一旦相対化するためにもプロトタイプを出していくんです。繰り返し繰り返しプロトタイプを作ることで、ちゃんと彼らの持っている経験や知識も引き出され、だけど今までとはちょっと違う場所にいけたかもしれないという感覚がプロジェクトの最後になると出てくる。それがプロジェクトに関わったメンバーの成功体験になっていくのだと思います。
それと、「何でこんなに使い勝手が悪いの? ユーザーテストしたの?」といった製品はたくさんありますけど、そういった足元の問題はプロトタイプを用いながら製品化の前にできるだけつぶしておいたほうがいい。プロトタイピングは予防注射のようなもので、回数を重ねることで、市場に出たときに失敗する確率がどんどん下がっていくんですよね。
だから、1回そういうプロセスに慣れてしまうと今までやっていたやり方がいかにあてずっぽうだったかが逆に思い返されるようで(笑)、そういった理由で一度ご一緒させていただいたクライアントの方々とは、継続的に仕事をさせていただく機会が多いのだと思います。
−−各クライアントさんとのインターフェイスはすべて田川さんがなさっているのですか。
そんなことはないです。クライアントごとに担当がそれぞれつきます。
−−それぞれの方が担当のクライアントさんに対してアウトプットしていくのですね。今は何社くらいクライアントさんをお持ちなのですか。
プロジェクトでいうと同時で10本前後ぐらいでしょうか。
−−すごいですね。やはり電子デバイス系が多いのですか。
はい、ハイテク系のプロジェクトはあいかわらず多いです。仕事の幅の広がりとしては、ローテクなもの、例えばシャンプーのパッケージや化粧品といったものや、アートインスタレーションの仕事も少なくありません。しかし、そういう分野を得意としていらっしゃるデザイナーさんは他にも多くいらっしゃいますから、僕らは数ある候補の中の1つということになるかもしれませんね。逆にハイテク系の仕事の場合には、頭を抱えるくらい複雑な仕様や制限のあるものがあって、そのような分野でこそ僕らの持ち味が生かされるのかもしれません。
−−ネットワーク系とか?
ええ、ネットワークの先のサービスまで含んだ話とか。僕らはユーザーが使うもののデザインの良さや、ユーザー体験としてそれがいいかどうかというところを見ていくんですけど、それはクライアントの企業からするとビジネスモデルと表裏一体です。だから逆にビジネスの話なのかデザインの話なのか分からないレベルで会話が交わされていきます。ユーザー側の操作感が良くないとか、ユーザー体験をするためにビジネス側がここは譲ってくれませんかという話とかも、打ち合わせの中でどんどんしていくようなタイプのものになっていきます。
−−クライアントから見ると、エンドユーザーの手前にtakramがいるような。
そんな見え方だと思います。ビジネスはこういうふうに考えているんだけれども、それがそのまま表現されるとユーザーから見たらグロテクスなわけです。だからそれを僕らが一応フィルターして、ユーザーから見てすっきりするにはこう再構成すべきなんじゃないかという。視線としては、僕らはユーザーサイドからビジネスのほうを見ているということですね。
●プロトタイプを作る意味
−−takramの仕事の評価が高いのは、プロダクトが成功しているからなのでしょうね。
多分それが売れたとか、ユーザーが増えたとかいう事実があるんでしょうね。
−−企業側の判断基準はある意味そこだけという気もします。
経営者たちは基本それですよね。デザインの良し悪しはあるんだけれど、最後は「それって本当にユーザーが増えた?」みたいな話になる。
−−それでどれだけ儲かったかという話。
自分たちのプロとしての価値を極限までシンプルに考えていくと、やっぱりその部分は無視できないポイントの1つだと思います。もちろんそれだけにドライブされてモノ作りしているわけではないですよ。しかし、プロトタイプをたくさん作ってこまめに失敗しておくことで、市場に出した後の失敗確率が下がるということは確かに言えると思うんです。
−−製品にする前段階でいろいろな経験をしてしまうのですね。
そうです。フォークやナイフや箸はすごくよくできていますけど、歴史の本とかを読むとものすごくたくさん失敗作があるといいます。失敗体験が今の四股のフォークに集約されているんですよね。フォークやナイフの製造技術にはもう大進歩というものはないので、失敗体験というか、いわゆる改善というものが製品に蓄積していく状況が整っているんですよ。技術的に進歩が止まっている領域では改善の積み重ねが効くんですね。
でも技術の進歩が激しい領域だと、去年の失敗が今年の参考にならない。だから、毎回毎回失敗してしまうんです。僕らのプロトタイプはそういう失敗体験の蓄積というところから見ると予防注射みたいなもので、製品をリリースする前に製品ライクなものでたくさんユーザーテストを行います。それで技術的にサービスリリースしたような状態を仮想的に作ってみる。そうしていくと、基本の足元のレベルでダメなところがいっぱい出てくる。それをつぶしてつぶして、もうこれで大丈夫だろうというところまでしていった状態にまで設計をならしていくんです。そうすると、いろいろな状況に耐える力が備わったものとして市場に出ていく。そうすると、なかなか風邪をひきにくいみたいな(笑)。
ヒットするかどうかはプロモーションや商流、それにタイミングなど、設計やデザイン以外のいろいろなファクターの掛け算になるので、出してみなければ分からないというところもあるのですが、少なくとも失敗確率を下げることはできます。だから、プロトタイピングは「もうあとは神のみぞ知る」というレベルにまで、プロダクトの品質を高めるだけのプロセスにはなっていると思います。
それは設計者のユーザーに対する誠実な態度という部分もあります。「いいか悪いか分からないけれど、市場で1回実験してみればいいじゃないか」というのは、少しいい加減なんじゃないかという気持ちもあって。
Googleなどのネットサービス系の会社は、もっとドラスティックというか、ベータ版でプロダクトを出してしまいますよね。設計やデザインは全部クラウド側にあるので、毎日大量にやってくるユーザーフィードバックやデータを見ながら日々改善をするというやり方がとれる。延々プロトタイピングしている感じですね。一方、日本のメーカーさんのプロダクトはたいていハードウェアが絡んでくるので、1回リリースして製品がユーザーの手元に渡ってしまうとそれに改良を加えることが難しいんですよね。なので、そういうベータ版的な、あとユーザーテストとかフィールドワークみたいなものを製品リリースよりも手前側で起こしてしまって、ある程度整理のついたもので出すというアプローチになっています。
−−そこがtakramの重要な役割。
面白い話なんですけど、専門家同士、エンジニアとビジネスマンが話していると、ビジネスマンはたいていビジネスの話ばかりするんですよ。それを聞いたエンジニアはきょとんとしていたりとか(笑)。逆もまたしかりでエンジニアが技術的な話を始めると、ビジネスマンは面倒くさそうな顔をしたりとか。そうでなくてもかみ合わないなというところはたくさんあるんですけど、プロトタイプがポンと真ん中にあると、ビジネスマンもエンジニアも自分が1ユーザーになった気分で話を始めるんですね。「それって使いにくくないですか」とか柔らかい言葉になって、人間として会話をし出すんです(笑)。そこがプロトタイプの魔力なのかなと。
−−プロトタイプの段階では、いわゆるデザイン的なニュアンスはあまり反映させていないのですか。
プロジェクトによりますよね。だけど、プロジェクトの最終段階になってくるとプロトタイプはほぼ製品の顔をしてきます。その段階になると、エンジニアリング的にもビジネスロジック的にもデザイン的にも非常に最終品に近い、とても完成されたものになってくるので、そこではデザインの話も細かくします。
−−最後はディテールを詰めるというよりは、やはりプロトタイプを追い込んでいく中で、作っている人間のデザイン的なニュアンスが反映されていくということですね。
そうですね。繰り返し繰り返しやっていくので、少しずつ、プロトタイプを作っている人のニュアンスが乗っていきます。プロジェクトには必ず1人リーダーがいるんですけど、デザインテイストについては、このリーダーのテイストが濃厚に出ます(笑)。ロボットは畑中の担当ですが、基本彼の世界観で作られています。GUIの仕事は僕がけっこうやっているんですが、これには僕の好みがあります。また「water」展に出した撥水加工した水のお皿。これは渡邉康太郎が担当していて、彼の世界観がかなりあります(笑)。takramの作品が全体的に白とか透明なのが多いのはなりゆきで、全然そうではない濃厚なものもあります。
−−アウトプットする際のtakramさんのデザインコード的な取り決めはありますか。全体的に「らしさ」はありますよね。
にじみ出てしまうレベルですかね。取り決めはないです。
−−違う個性を持った何人かの方がそれぞれの世界観を持ちながらも「らしさ」が出るというのはどういうことなのでしょう。
僕らはプロジェクトが出る直前に、品評会までではないですけどみんなで見て、あれやこれやと議論します。そこでテイストの話はしませんね。テイストとか方向性はその人の味で、それを「NO」と言ってしまってはもう何もできないですから。むしろ「そっちの方向を向いているんだったら、このレベルはこのクオリティ感までいかないとまずいよ」みたいな話はします。最後の詰めですね。
−−「らしさ」というのは難しくて、例えばシャープの製品にソニーのロゴを貼ったらソニーの製品に見えてしまうのではないかと思うのですが、takramでは各クライアントさんの「らしさ」を意識されるのですか。
しますね。しますし、メーカーさんの「らしさ」というのもあるんですけど、その先には必ず使う人がいて、それは誰なんだろうということを考えながら、プロトタイプを作っているうちに自然とその味が出てしまいます。この製品は誰が使うんだろうというのを見ていくと、色や形、大きさや重さという話をどうしても考えないといけない。それを考えていくと、少しずつメーカーさんの目指すところにも合っていきます。
そして、クライアントの方々はプロトタイピングの過程でたくさんのアイデアやコメントを出してきます。プロトタイプはそういったサイクルを重ねていった結果なので、必然的にメーカーさんの味が反映されていきます。
[Page 02]
|