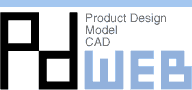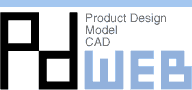●デザイナーを目指した少年時代
−−小牟田さん自身、名刺の肩書きに「デザインプロデューサー」と入れていらっしゃいますね。デザインプロデューサーというのはどういった仕事なのでしょう。
小牟田:その言葉自体にそれほどこだわりを持っているわけではありません。僕はデザイナーではないし、デザインディレクターというにはディレクション以外の知見も必要で、経営や事業のことを考えてデザインやモノ作りと結びつけることをやっています。典型的な立ち位置のない、時にはディレクターであったりプロデュースであったり。いつでも変えられると思っています、肩書き(笑)。
−−小牟田さんの社会人のスタートは、カシオのインハウスデザイナーでしたが、学生の頃からデザイナーを目指していたのですか。
小牟田:僕は神奈川県立の弥栄高校の2期生だったのですが、この高校には美術コースと音楽コースと、それから一般コースがありました。美術の大学を目指す人は美術コースなのですけれど、弥栄高校から多摩美術大学のプロダクトデザイン科に一番最初に受かったのが一般コースにいた僕だったんですよ。
−−美術やデザインはもともと好きだったのですか。
小牟田:父がソニーのエンジニアだった影響もあって、自分もモノ作りの仕事をやるのだろうとは思っていました。子供の頃から僕が何に興味を持って何を壊してもいいようにと、父がオーディオやスピーカーをゴロゴロと用意してくれていました。
中・高校生の頃には音響機器よりも自動車への興味が高まってきました。小学4年生くらいの頃に近所のお兄さんからもらった自動車雑誌を見て知ったのがカーデザイナーという職業でした。こんなデザイナーになりたいという思いを持ったまま、中学、高校と進んだのですが、詰め込みタイプの勉強が嫌いだったこともあって、当時の僕の成績ではエンジニアという道は無理だと気付きました。そこで好きでない勉強でモノ作りの道を目指すよりも、最短でかつ好きなルートからと探した結果が、工業デザインでした。
−−そういう意味では、小牟田さんの中ではデザインとエンジニアは区分されていなかったのですか。
小牟田:はい。とにかく、モノ作りをしたかったので。立体のモノを作る以外には視野にありませんでした。だから、多摩美術大学だったら自分の偏差値でも行ける可能性があると感じました。ですが、受験を決めたはいいものの、絵を描くという一番大事な試験があることは知らないままに受験宣言をしてしまいました。それでも、たくさん絵を描くことは、好きでもない科目の勉強するよりもはるかに近道に思えたこともあって、受験勉強はものすごくがんばりました。それこそ、本気でやりました。
−−一般コースに在籍されていて、いつ頃から美術大学に進学することを決めたのですか。
小牟田:高校3年生の5月頃です。それまでは高校野球をしていました。当時は弱いけれど練習が厳しいと有名な部で、僕より体格も才能も恵まれている仲間たちが辞めていくんです。残ったのは2割くらいしかいない野球部に、3年間、才能もない僕が引退試合まで続けていたことが、自分の中ではそれまでに味わったことのない大きな達成感を感じました。それが信じられないぐらいに強い自信につながって、なんでも気持ち1つなのかなということを17歳で強く意識したのですね。
美大に入ることを目的とするのではなく、工業デザイナーになることが明確な目的だったので、プロダクトデザイン系の学科だけを受験しました。美術大学に入るのはあくまでも僕の中ではプロセスだと思っていたんです。
僕は17歳の頃に「美大を出て、デザイナーとして活躍して、青山に事務所をもってベンツに乗る」って言ってたんですよ。周りに宣言してしまうことで自分を鼓舞しようと考えて。その当時は夢あってイイよねって言われつつも、大ホラを吹いているようで周囲から引かれるわけですけれど、自分だけはホラだと思ってはいけないと考えていました。今振り返ると、紆余曲折したけれども、フォーカスさえ外さなければ到達が可能なのだと、目的を持つことの重要さを実感します。
−−野球部の3年間で得たものは大きかったですね。
小牟田:「気合!」を手に入れたんですよ。工業デザイナーになる人たちは幼少の頃から絵が得意でプラモデルを作ってきて手先の器用な人ばかりだと思っていました。そんな中で不器用でバリバリの体育会系がいてもよいのではと思ったんです(笑)。でも実際には、優れたデザイナーさんは体育会系の方って多いですけどね。
●カシオでのデザイナーの日々
−−多摩美を卒業されてカシオに入社されたのですね。
小牟田:自動車デザイナーになりたいと思っていましたが、きっと自動車は一生好きなのだろうから、それを職業にしてしまうのはどうなのだろうなと思いはじめて。大学3年生のときに自動車製造関係の工場見学と研修に、授業の一環で連れて行ってもらったんですけれど、そのときに自動車方面にいかない方がよいなと思いました。僕には専門性が強すぎて、自動車以外にももっと多くのプロダクトに携わる可能性を感じたかった。
−−好きなことは大事にとっておこうみたいな。
小牟田:はい。でも、今の僕からすれば自動車にいってもよかったかなと思います。リサイクル系のアプローチで、自動車の業界でなにかできそうな気がしています。
−−では、カシオはいくつかの選択肢のうちの1つだったのですか。
小牟田:そうですね。バブルの頃で就職は売り手市場のはずだったのですけれど、僕は生意気だったので、企業の実習を受けてもご縁がいただけなくて。そこで、できるだけハイテクなモノをコンパクトに作る会社に入りたいと考えました。当時デザインセンターが原宿にあったという土地柄の魅力もあって、カシオにお世話になることにしました。
それが今につながるのですが、その頃から人が身に着ける、一番人の肌に近い精密機器を手がけたかったのです。当時カシオには電子手帳というプロダクトがあって、電子手帳系のプロダクトデザイン部門への配属を希望しました。
−−なるほど。
小牟田:ときどき使うデジタル機器ではなく、肌身離さず毎日持っていると、モノなのに愛情を注ぐ対象になる。そういったモノを作りたかった。
−−カシオといえば時計も有名ですし、肌に近い精密機器ですが、時計にはいかなかったのですか。
小牟田:時計は職人的な要素もあって僕には専門性が強いと思ったので。
−−電子手帳というとアップルのNewtonなどが出てきた頃ですね。日本でも各メーカーが独自の技術を競っていました。
小牟田:Newtonはすごいと思いました。でも、早すぎるなって。僕iPhoneをみたとき、Newtonがやっと完成したのだなと感想をもらしたりしましたけれど。
カシオでは当時Newtonのメッセージパッドの対抗手としてZoomerという機種があって、僕はまだ駆け出しだったので、先輩がデザインしたもののお手伝いをさせてもらっていました。すごく勉強になりましたよ。
シャープさんはZaurusを展開していて、そこに対して、カシオはWindowsCEを搭載したCASSIOPEIAを投入しました。その初号機、2号機のデザインを僕が担当させて頂きました。
−−CASSIOPEIAのようなキーボードを搭載したシェルタイプのデバイスも人気でしたよね。海外からはHP95LX、HP200LX、JORNADA、Psionなどいろいろありましたが、意識されていたのですか。
小牟田:特にはしていませんでした。
−−カシオ時代からデザイナーとしてではなく、もう少し上流から仕事をしていたのですか。
小牟田:そうですね。カシオに在籍していたのは10年ですが、自分でこういうことをやってはどうか、とか、考えつくとトータルでいろいろやりたくなるんですね。時として自分のミッションと違うことをやりたくなるといいますか、単なる好奇心ではなくて、こうするとお客さんに対して効果的にカシオというブランドを伝えられるんじゃないかと考えるんですね。でもそれは20代の担当レベルで及ぶ話ではないですよね。やはり、最低限課長クラス以上の仕事になるので、一般的にはとてもハードルの高い事な訳です。でも僕は、成功したときの手柄などはどうでも良いので、トータルでのデザインがやりたいのでやらせて欲しいと上司に言っていましたね(笑)。
人に喜んでもらうモノ作りを心がけていたのですが、数多くのことをやろうとすると、自分が一担当の職人として関わるだけのやり方では時間とパワーに限界があるなということに気付いたのです。
●カシオからKDDIへ。プロデューサーへの道
−−元々、小牟田さんはプレイヤー指向ではなく、プロデューサー指向ですよね。プレイヤーはもっと目の前にあるモノのディテールの追求にエネルギーを注ぎますが、小牟田さんは、トータルでみるタイプと言いますか。
小牟田:おそらくそうですね。今は形状のディテールは僕が考えることではないと思っています。それを検討するのにものすごい時間を職人時代には費やしますが、それは今までに十分やらせてもらいました。むしろ今はそういった経験をベースにして、もっと効率良く幅広く貢献できる方法を考えたいと思っています。
それから、僕はいつも良い上司に恵まれました。カシオも、KDDIも全員素晴らしい人しかいないです。皆さんにとてもかわいがっていただいて。生意気だけど指示には猛進しますから。だから不良でよかったなと思いますね(笑)。
−−カシオという器がだんだん自分の中で小さくなってきたのですか。
小牟田:ということでもないです。カシオほど僕を評価してくれた会社はないと思っていました。だけど一方では折角の人生、もっと違うところで勝負してみたいという好奇心もありました。
カシオが嫌で転職を考えるわけではないし、むしろとても伸び伸びと自由に楽しく仕事とチャンスを与えてくれていた。もしそれ以上の条件がつくのであればと、ジョブホップにこだわっていました。
当時まだ今のように転職がメジャーでない頃、いくつかの転職会社さんに自分の経歴を売り込んでみたことがありました。その中の1社さんとは3年近くお付き合いをさせていただいていたのですが、3年も経つ頃には、当初は転職を目的としたはずが転職自体に意味がないような気がしてきました。本当に使える人間はどんな会社をも発展に導く力を発揮するのではないかなと思ったのです。
そんな中、登録していた転職会社の1社さんからKDDIさんの紹介が来たのです。でも、通信会社にはデザインセンターもないし、モノ作り系統の人がいるかどうかも疑わしい。工業デザインといった狭い業界の職人を何で欲しいのか分からなくて。
そうしたら、KDDIは当時IDO、DDI、KDDの3社が合併をして「au」というブランドに全国統一したばかりで、これからデザインに力を入れて、デザインで他社に勝っていきたいと考えているという説明を受けて、とても興味を持ちました。
当時は携帯電話機メーカーの参入数がピークだった頃で、客観的に見ると携帯電話のデザインは似たり寄ったりな印象を強く受けていました。僕は、今のデザインよりも良くするのは簡単ですよと言ったのです(笑)。でも投入のタイミングや価格など、ビジネスではそういったものすべてがそろっていないと駄目じゃないですかと。
それがたぶん響いたのでしょうね。「あなたに全部まかせるから、自由にやってくれ」って言葉をいただき、しかも部屋まで用意してもらいました。ただ入社したものの、モノ作りに携わる人が他に見当たらないので戸惑いましたけど。
−−当時、砂原さんはいらしたのですか。
小牟田:デザイナーを採用しようという発案は彼だそうです。デザイナーを雇ったらいいのではというのを当時の部長と砂原さんで話し合っていたようです。
−−基本、通信キャリアというのはメーカーから端末を買っていましたから、小牟田さんの役割は、開拓しないと駄目ですよね?
小牟田:自由にやっていいと言われたものの、分野が違いすぎて(笑)。僕はマーケティング部で一応チーフデザイナーという肩書きでしたけれど、僕1人だけなんです(笑)。砂原さんもマーケティング部で、一生懸命勉強していた時期でした。とりあえずメーカーのミーティングには必ず出てくれと言われて、当初は朝から晩までミーティング三昧でした。メーカーの試作モデルを拝見して改善ポイントを指摘して説明するのですが、専門用語を使って話をするので、KDDIの人から「こむちゃんの言うキーワードは素人にはさっぱり分からん」と笑われました(笑)。彼らにはデザインの話がすごく新鮮だったようです。でも次回修正されたモデルを見て、「こむちゃんの言う通りやると全部良くなる!」という風にだんだん理解されるようになってなってきました。
−−当時のキャリアには端末のデザインをジャッジする視点はなかったですよね。
小牟田:僕は間違いなく世界初の通信キャリアのインハウスデザイナーなので、前例がないんですよ(笑)。ですから、一方で通信の世界の初歩的な話からいろいろと教わりました。
−−端末のデザインは、auだけではなく業界の問題でしたよね。キャリアにデザインプロデューサーがいるというのは、メーカー側から見ると初めての経験ですね。
小牟田:だからメーカーさんは嫌だったと思いますよ。僕はメーカーのデザイナーさんに「僕はみなさんのデザインがお客さんのための正義であれば、それをできるだけ具現化するためにいると思ってください」って話をしました。ですから、デザインディレクションというよりは「モバイルプロダクトディレクター」ですよね。
−−当時はまだ携帯電話といえば黒かグレーみたいな時代でしたよね。
小牟田:そうですね、カラー化を進めようと考えたのは実は僕なんです。当時はまだ今のように豊富なカラーバリエーションの端末は出ていませんでした。
それからもう1つ。当時僕はどうしても深澤直人さんと仕事をしたかったんです。深澤さんと一緒にやりたいというのは、カシオにいたときから思っていて、実はKDDIに入社して数日後には深澤さんにお会いしました。
[Page 02]
|