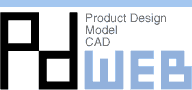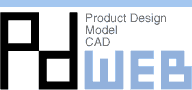|


「TSUTSUNUKE soil spoon」(2005年)(クリックで拡大)


「TATEOKI watering can」(2005年)(クリックで拡大)


「TRASH POT」(2004年 - 2008年)(クリックで拡大)


「靴べら」(クリックで拡大)


モビール「constellation(星座)」(2001年)(クリックで拡大)

「Paper-Wood / plywood lab.」(2007年-)(クリックで拡大)



|
 |
−−ドリルデザインさんのこれまでの経緯と活動内容、主な作品について、設立当初からざっと振り返っていただけますか。
林:僕は大学は経済学部で経済地理学を学んでいました。大学を卒業してデザインの専門学校(ICSカレッジオブアーツ)に入り、そこでインテリアデザイン、建築、家具などを学び、その同期4人でドリルデザインを立ち上げたのが2000年です。
−−経済地理学からデザインの道への方向転換は、どういったきっかけからだったんですか。
林:僕は昔からモノを作ったり絵を描いたりとかが好きだったんですけど、フリーのプロダクトデザイナーの存在を知らなかったんです。こういう仕事があるというのは大学のときに知って(笑)。
大学のゼミでは、ある農村に行って調査をするとか、そういうフィールドワークをしていたんですが、地域、現地の経済的な問題など、調べれば調べるほどいろいろ出てきました。でも、学問の範囲内では現状分析まではするけど、解決策は国なり行政なり、あるいは建築家、モノを作る人が考えるということなんです。
そこで僕自身が、そういう問題解決も行いたいという気持ちがあったのと、当時、すごく不景気で、金融ビッグバンがあって大企業の終身雇用の信用が崩れたときだったんですね。経済学部だったので銀行など就職先はあったんでしょうけど、どこに入っても何か保証されるわけではなく、それなら何か自分でできることを身に付けた方がいいなということで専門学校に行きました。
その当時、デザインがちょうどブームになりかけの頃というか、イームズなどのミッドセンチュリーの家具が日本に入ってきて、こういった自由なモノ作りが行える、プロダクトデザインの仕事を知りました。
−−独立系のデザイン事務所はインハウスの経験を経て設立される方が多いと思うのですが、林さんはドリルデザインを未経験で始めました。今はそういう人も多いですけれど、先駆けですよね。
林:そうかもしれないですね。就職できなかったというのもあるかもしれないんですけど(笑)。でもほとんど成り行きです。
専門学校を卒業して、あるコンペに作品を出そうと同級生で始めたのがドリルデザインの始まりです。最初の頃はグループ展やコンペに出すばかりでした。普通は、しばらくやってみてダメだったら就職考えようかみたいになるんですけど、続けられたきっかけとして、リビングデザインセンターOZONEのプロデューサーだった萩原修さんに出会えたことです。自己紹介で、デザインの学生で卒業したばかりなんですって言ってたら、「グループ展に出ない?」という話をいただき、そこでモビール展に出させていただきました。
僕らは、経験はないけど時間だけはあったんです。だから、1点だけの展示では面白くないから、自分たちがデザインしたモビールを100個くらい量産しました。それが2週間の展覧会で完売したんですよね。それでOZONEの人たちが気に入ってくれて、グループ展があると呼んでくれたり、展覧会の会場のデザインを任されたり、広がっていきました。「グラフィックもできる?」「やったことないけど多分できます」みたいな感じでした(笑)。依頼があれば、勉強しながらなんでもやろうというスタンスでした。それが2001年の頃です。
−−モビールはずっと続いているプロダクトなのですか。
林:去年までは切れていたんですけど、デザイナーの村澤一晃さんがmother toolでモビールをデザインして、1つだけmother toolのラインナップにあってもどうしようもないからと、うちに「林くん、前やってたモビールやらない?」とお誘いを受けて、また動き出したんです。今は、どうせならモビールブランドを作りましょうという話で進めています。モビールはすごく面白いプロダクトだと思うし、部屋にポンと吊ってあると雰囲気が変わりますよね。でもその魅力はまだ浸透してないと思うのです。
キャラクターっぽいかわいらしい路線のものじゃなくて、もっとモダンで幾何学的な、どんな大人っぽい空間でもピシッと入っていくようなモビールを作りたいねという話なんです。
−−モビールは絵画っぽい、グラフィカルなイメージもあって、インテリアにもなるし、部屋の雰囲気を支配できますよね。
林:そうなんです。アイデアも入れられるし、純粋に彫刻っぽい、オブジェとしても楽しめます。
−−なるほど。モビールがドリルデザインの原点なのかもしれませんね。
林:まあそんなことをやっていて、それでぽつぽつ仕事が入るようになって、初期の頃は地方の、特に四国の仕事が多かったです。たまたまOZONEで四国のメーカーと東京のデザイナーのマッチング事業みたいな企画があって、「TRASH POT」という紙製のゴミ箱を松山の会社で作って発表しました。
それを四国の東予産業創造センターの局長が気に入ってくれて、いろいろな会社を紹介してくれました。それが2004年、2005年頃です。アッシュコンセプトと出した積み木の「ヒューマンブロック」も高知で作っていました。
−−最近の作品を教えてください。
林:転機になったプロダクトというのでは、今「合板研究所」で新しい素材を作っています。
−−素材ですか。
林:はい。合板、プライウッドですね。普通は木目を交互に挟んで板を作っているんですけど、そこにいろいろな素材を挟んだら面白いんじゃないかということで、FULL SWINGという東京・多摩にある木工所の人たちと、合板は可能性があるからいろいろなもの挟んで実験してみようと合板研究所を立ち上げました。
毎月、挟みたい素材を持って集まるワークショップを行っていて、アクリル、樹脂系、布系、発泡剤とかいろいろなものを挟んだ中で、偶然印刷所で分厚い、小口まで色の入った紙を見つけたんです。その紙を挟んでみたらかなりいい。新しい使い方、可能性を想起させるんです。これまでの合板は、小口をいかに隠すかという発想でしたが、逆に小口をどう見せるか。どういうふうにカットしたら面白い見え方がするかとか、そういうことを想起させる新しい素材が作れるんじゃないかというので。これは「Paper-Wood」の名称で商品化されました。
そもそもインテリアライフスタイル展のneONというコーナーに出展し、そこで北海道の会社が気に入ってくれて、そこでまた1年ぐらいかけて実験や強度試験などを行い、2010年に商品化されました。その年のグッドデザイン賞もいただき、現在はインテリアの棚板やテーブルの天板、住宅の階段の板などいろいろな場所で使われるようになっています。
これは今までプロダクトとかモノを作っていた中で、何か素材からモノ作りができないかというのでやって、すごく可能性を感じているんです。「Paper-Wood」をうちの作品として家具にするという方法もあったんですけど、誰もが使える素材として流通させたほうが広がっていくし、可能性があって面白いですよね。
−−ここ数年で、ドリルデザインのプロダクトの数がすごく増えていますよね。急成長されているなという印象がすごくありますが、いわゆるプロダクトデザイン系では最近は何がありますか。
林:最近は家具のデザインをしていて、VILLAGEという椅子がTIME&STYLEという家具メーカーから出ています。これはウィンザーチェアという形式をベースにしているんですけど、日本の空間に合う椅子を作ろうというシリーズです。家具のデザインはすごく楽しいというか、もともと家具を手がけたかったんですよね。
2ページへ

|